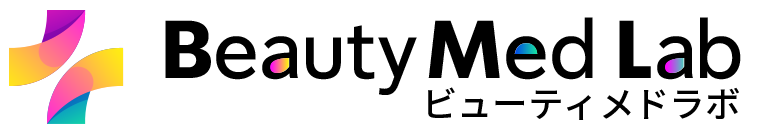「ちゃんと説明しているつもりなんです。でも、伝わらないんですよね」
美容クリニックを経営する院長たちから、何度となく聞いてきた言葉です。
理念も伝えている。目標も示している。制度だって整えてきた――それでも、スタッフは“自分事”で動いてくれない。提案しない、考えない、目の前の仕事だけを淡々とこなしているように見える。

スタッフを入れ替えても、同じことが起こる。
評価制度を導入しても、数字は動かない。
「私の伝え方が悪いのか」「人材に恵まれていないのか」
そんな自問を繰り返すうちに、疲れを感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「なぜスタッフは売上や患者満足を“自分事”として捉えられないのか」を、行動の背景にある“感情”や“構造”から読み解きます。
叱るでも、諦めるでもない。“伝え方”でも“制度”でもない、もっと根っこの部分にある「ズレ」をやさしく言語化してみたいのです。
スタッフを変えても、景色は変わらなかった

「あの子じゃダメだ」から、「誰でも同じかもしれない」へ
「なんで、またこうなるんだろう」
ある経営者がぽつりとつぶやいた。売上も、患者満足度も、停滞したまま。思い切ってスタッフを入れ替えてみた。前任より意識高そうだったし、笑顔も申し分ない。それでも、数ヶ月後に目にした現場は、以前とほとんど変わらない景色だった。
美容医療の現場は、外から見れば華やかで活気がある。でも中に入ってみると、どこか空気が重い。誰かの責任のように思えて、つい「この子がダメなんじゃないか」と人に目が向く。でも数人繰り返してみて、ようやく思い至る。「これは、人の問題ではないのかもしれない」と。
売上は“数字”なのに、“気持ち”が動かない
売上というのは、感情を持たない。ただ、結果を数字で突きつけてくる。でも人は、感情で動く生き物だ。月末に数字を共有しても、スタッフの反応は「ふーん」で終わる。そこに悔しさも、やるせなさも、あまり感じられない。
「この数字がどうして出たのか」「何が足りなかったのか」まで一緒に考えてほしいのに、届かない。たとえ売上に応じたインセンティブを設けたとしても、それだけで心が燃えるわけではない。数字が“自分の人生”にどう響いているか、スタッフが実感できなければ、ただの他人事になるのだ。
「このままじゃダメ」なのは、スタッフより経営者の方
売上未達。患者数の減少。口コミの停滞。
あれもこれも気になって、院長の心はいつも落ち着かない。
その一方で、スタッフは淡々と目の前の業務をこなしているように見える。イライラしながら、つい口調が強くなる。「ちゃんと考えて動いてる?」「もっと責任感持ってよ」。
でも、本当に“伝わっていない”のは誰の言葉なのか。スタッフの無関心に見える態度は、もしかすると、“理解できなかっただけ”の反応かもしれない。経営者の焦りと、スタッフの鈍さ。その温度差に、まず気づくことからしか始まらない。
場の空気は、入れ替えただけでは変わらない
「空気」というのは不思議なものだ。誰かが辞め、誰かが入っても、その場に残る“気配”がある。前任者のせいだと思っていたけれど、新人が入ってもまた同じように受け身になる。提案しない、意見を出さない、動かない。
これは、スタッフの資質ではなく、「この場では、何を言っても通らない」と思わせる雰囲気が染みついているから。そういう空気に、どんな優秀な人が入っても、いずれ同じ表情になる。
変えるべきは、人ではなく、空気――。それに気づいたとき、はじめて「じゃあどうする?」という問いが生まれるのだ。
スタッフが「売上=自分事」にならない理由

売上は“現象”であって、原因じゃない
売上が下がった。そんなとき、経営者は原因を探す。「カウンセリングの質が落ちた?」「リピーターが減ってる?」と、現場をにらむ。でも多くのスタッフは、「今日は売れなかった」で終わってしまう。そこに“なぜ”がない。
売上は、彼女たちにとって“空から降ってくる結果の数字”のようだ。誰かが頑張って取ってくるもの。自分はただ業務をこなして、そのあとに表示されるスコアに過ぎない。言い換えれば、「患者が来るか来ないか」で決まるものであって、自分の言動で左右できるとは思っていないのだ。
この乖離は意外と根深い。
売上とは“行動の結果”だと気づいていない限り、自分の何をどう変えたら売上に影響するのか、わからないまま働きつづける。そしてその“わからなさ”こそが、無関心の温床になる。
「売ること」が悪いことのように感じている
「それって、ちょっと押し売りっぽくないですか?」
カウンセリングの練習をしていたとき、あるスタッフがつぶやいた言葉だ。その一言に、この業界の難しさがにじむ。美容医療という商品は、本人の“気づき”があって初めて成り立つ。でもその気づきを促す行為が、提案ではなく“売り込み”に映ってしまうことがある。
しかも今の若い世代ほど、“売る”ことに抵抗感が強い。「自分がされて嫌なことは、したくない」という感覚が、強く働いてしまう。その優しさが裏目に出て、「本当は必要だと思っても、あえて言わない」という行動につながるのだ。
「売上を伸ばそう」と言えば言うほど、“強く売れってこと?”と誤解される。提案とは、相手の未来を良くするための会話である。その線引きを、きちんと教え、何度も体験させることがなければ、彼女たちは“売らない安心”に甘んじてしまう。
“売上を追う人”が、ちょっと浮いてしまう職場
あるスタッフが頑張って、ヒアルロン酸のコースを複数成約した日があった。経営者としては嬉しくて、「よくやったね!」と称賛した。ところが、その後スタッフ間に奇妙な空気が流れた。
「あの子、最近ちょっとギラついてない?」
「なんか売上しか見てない感じで、苦手」
売上を出すスタッフが、逆に浮いてしまう。そんな構図はどこのクリニックにもあるかもしれない。「頑張る子」が称えられるどころか、“一線を越えた人”のように扱われる。そうなると、誰も頑張ろうとしなくなる。だって、浮きたくないから。
評価されるのは“安全な普通”ばかり。そんな空気が染みついた職場では、「自分事で売上を追う」という行為が、リスクにすら感じられてしまうのだ。
数字だけ示されても、“自分への意味”がわからない
「今月の目標は売上〇万円。今、ここです」
毎月の朝礼や週報でグラフが示される。でも、どんなに丁寧にスライドをつくっても、スタッフの表情は動かない。それは“その数字が自分とどう関係あるのか”がわからないからだ。
人は、「その行動が、自分にどう返ってくるか」が見えないと、心が動かない。昇給?インセンティブ?評価? それが実感できる人は、ほんの一握り。ほとんどの人は、「まあ自分には関係ないかも」で済ませてしまう。
「あなたのひと言が、患者さんの“また来たい”につながってるんだよ」
そういう“意味の橋渡し”が、どれだけ現場でなされているか。その伝え方ひとつで、売上という“冷たい数字”が、自分の“あたたかい経験”に変わるかもしれない。
「提案する」ことの本質と誤解

“売らない”ことが、やさしさだと思っている
あるスタッフが患者対応を終えたあと、「必要なさそうだったので、無理におすすめしませんでした」と報告してきた。
その言葉に、院長として思わず口を閉ざしたくなった。
やさしさ。それは確かに大切なことだ。でも、その“やさしさ”が、時に患者さんの未来の選択肢を奪っていることもある。
スタッフ自身は、「押しつけるのはよくない」と思っている。むしろ遠慮がちに接するほうが誠実だと信じている。でも、本当にそうだろうか?
本当は悩んでいる人に、「あなたにはこういう選択肢もありますよ」と伝えることは、押し売りではない。
提案しなければ、患者さんは自分の可能性にすら気づけないかもしれない。それは“やさしさ”という名の“無関心”かもしれないのだ。
「必要ないですか?」は、“いらない前提”の会話
「こういう治療もあるんですけど……必要ないですか?」
カウンセリングの場面で、こうした尋ね方をするスタッフは少なくない。たしかに聞こえは丁寧。でもその裏にあるのは、「断ってくれてもいいんですよ」という前提だ。
提案とは、本来「あなたのために、本気でおすすめしたい」という意思の表れである。
それが「必要ないですか?」という言い方になる時点で、本音は「断ってもらってホッとしたい」なのかもしれない。相手の反応を恐れ、断られることで自分を守ってしまっている。
本当にその治療が役に立つと信じているなら、「なぜこれがあなたに必要なのか」を伝える言葉になるはず。
スタッフ自身がその価値を腑に落としていないからこそ、“逃げ腰の提案”になってしまう。
“営業トーク”と“信頼を深める会話”のちがい
提案と聞くと、多くのスタッフは「営業トーク」と思いがちだ。「決まり文句のように商品説明をすればいい」と。けれど、それでは患者の心は動かない。
大切なのは、“この人の未来”に寄り添う視点だ。
ただ「これをやるとキレイになりますよ」と言うのではなく、「あなたが気にしていたここの印象を、こう変える方法もあるんですよ」と、“なりたい姿”を一緒に描いてあげること。
営業とは、“買わせる行為”ではなく、“選ばせる環境を整える行為”だ。
そして、それはテクニックではなく、信頼の上にしか成り立たない。
信頼を深める会話とは、相手を理解し、想像し、願いを代弁する会話である。そうした時間を共に過ごすことが、自然と“売上”につながっていく。
「売りつける」のではなく、「届かせる」こと
患者さんの多くは、自分の悩みを正確に言葉にできていない。
「なんとなく気になる」「最近、老けて見える」――その曖昧な感情の奥にある“願い”を見つけ、言語化してあげること。それが、提案の本質である。
「あなたにとって、こうなれたら素敵だと思うんです」
「もし私があなたの立場だったら、こういう治療を選びたいと思います」
そんな共感ベースの言葉が、患者の心を開く。売るのではない。届けるのだ。
“本当に伝わった提案”は、患者さんの顔をほっとゆるませる。
その瞬間、スタッフ自身も「ああ、やってよかった」と感じるはずだ。
それが、売上を追うことの“気持ちよさ”と“正しさ”を、はじめて教えてくれる。
なぜ自分事にしてくれる人は希少なのか

「自分で考えて動く人」は、“生まれつき”じゃない
「うちは何人雇っても、結局1人くらいしか“自走”しないんですよ」
あるクリニックの院長が、ため息まじりにそうこぼしたことがある。確かに、最初から能動的に動けるスタッフは少ない。指示を待たずに患者さんと会話し、提案をし、行動できる人――そんな存在は、どこの職場でも“例外”扱いだ。
でもそれは、“本人の性格”だけの問題ではない。
多くの場合、そうしたスタッフは「そういう環境」で育ってきた。家庭で責任を任された経験がある。前職で挑戦のチャンスを与えられてきた。自分の言動が誰かに影響を与えるという実感を、若いうちに何度も味わってきた。
つまり、「自分で考えて動く人」は、たまたまそういう経験値の中で育った“偶然の産物”だ。
もし、現場がそういう経験を積める環境になっていないのなら、同じような人材は、これからもずっと生まれない。
“褒められて伸びる”世代の限界
今の若い世代は、「否定されること」にとても敏感だ。
それは悪いことではない。けれど、“褒めて育てる文化”が当たり前になった反面、“褒められなければ動かない”という副作用もある。
何をすれば評価されるのか。誰が見てくれているのか。それが明確でないと、不安になってしまう。
「提案してみたけど、特に反応がなかった」と落ち込む姿を見て、思わず声をかけたくなることもあるだろう。
でも本当は、他人からの評価より、「自分で納得できたか」のほうがずっと大切な軸だ。
スタッフが“自分事”で動けるようになるには、「自分なりの価値判断」を持つ経験が必要なのだ。
ただ褒めればいいわけじゃない。
“自己評価”を育てるには、「なぜそれがよかったのか」を伝えること。そして、本人が“気づく余白”を与えること。その繰り返しが、少しずつ“主体性”を育てていく。
やらされ仕事から、“意味づけ”のない現場へ
「言われたからやる」
「決まっているからやる」
そんな仕事の仕方に慣れてしまったスタッフに、「自分で考えて」と言っても、そもそも“考える癖”がない。いや、考えてもムダだと思ってきたのかもしれない。
過去の職場で、自分の意見が通らなかった経験。やる意味もわからないルールに従わされた日々。そうして、だんだんと“思考を止めるクセ”が身についていった。
そして気づけば、誰かに言われたことだけをこなす“効率的な働き手”になる。けれど、それでは売上にはつながらない。美容医療の現場は“共感”と“提案”があってこそ成り立つのだから。
「この行動に、どんな意味があるのか」
その意味づけを与えないまま、「自由にやっていいよ」と言われても、人は動けない。
まずは“意味を共有する文化”を、院長側が根気強く作っていくしかない。
“偶然できる子”に頼っても、場は変わらない
たまに、最初から提案ができて、売上も上げて、患者にも感謝される“スーパースタッフ”が現れる。院長はつい、その子に依存してしまう。「あの子がいれば、なんとかなる」と。
でも、その子が辞めた途端に、現場がガラガラと崩れるケースもある。それは、構造ではなく“個人の資質”に頼ってきたから。
たまたま自走できる人材が1人いただけで、現場全体の“自分事文化”が育っていたわけではないのだ。
偶然に頼るマネジメントは、運任せに近い。
誰が来ても育つ現場とは、「気づく」「試す」「意味を考える」という“体験”を、意図的に組み込んでいる場である。
育てるとは、待つことではない。整えることだ。
その仕組みがなければ、“自分で動ける人”はいつまで経っても“レアキャラ”のままなのだ。
経営者がすべき“育てる仕組み”3つの視点
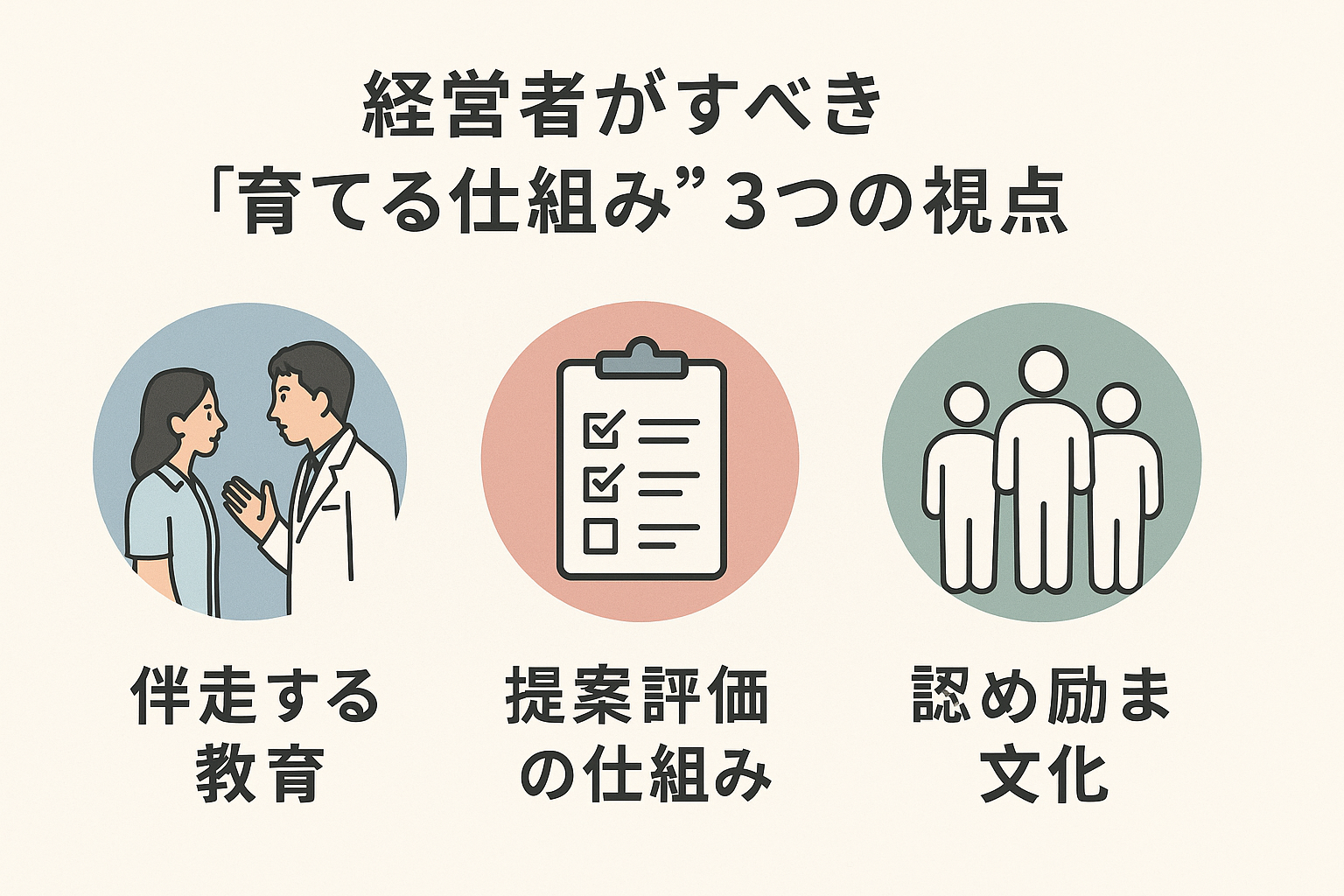
行動 → 結果 → 喜ばれた、を“見える化”する
人は、結果が出たときよりも、「その結果が誰かの喜びにつながった」と実感したときに、最も心が動く。
「売れました」と言われても、数字で終わってしまうと、本人の中に残らない。
でも、「患者さんが“あなたが勧めてくれてよかった”って言ってたよ」と伝えるだけで、世界の色が少し変わる。
“売上”は目に見える。でも“感謝”は、目に見えない。だからこそ、経営者が意識的に“見えるようにする”必要がある。
たとえば、カウンセリングのあとの患者さんの声をスタッフにフィードバックする。
たとえば、施術後のアンケートに一言「〇〇さんの対応がよかった」と書かれていたら、それを朝礼で共有する。
小さな“ありがとう”を伝えるだけでも、「あ、自分のあの一言が届いたんだ」と思える。
その実感の積み重ねが、「またやってみよう」という行動の種になる。
育てるとは、気づかせて、つなげて、灯すこと。その流れを“仕組み”としてつくっていくのだ。
「数字を追う」と「誰が喜ぶか」を言語化する
売上目標を提示して、「今月は4000万円を目指します」と言う。その数字に、スタッフがピンとこないのは当然だ。
“数字”は感情を持たない。だからこそ、“その数字の向こうにある人の顔”を、言葉にして届けていくことが大切だ。
「今月、もう少し頑張れたら、新しい機械の導入が見えてくる」
「あと10人の患者さんが、もっと自分の顔を好きになれるかもしれない」
「この施術が安定すれば、〇〇さんの業務負担が減る」
売上の向こう側には、たくさんの“人の物語”がある。
スタッフにとってのモチベーションは、報酬だけではない。
“自分の頑張りが、誰かを助ける”という実感があってこそ、“自分事”になる。
経営者にできるのは、その“意味づけ”を、日々の言葉で手渡すこと。
目標を“数字の押しつけ”ではなく、“共通の願い”として届けられるかどうか――そこに、現場の温度が左右される。
“やる気”ではなく、“構造”で動かす
「やる気の問題ですかね」と口にする経営者は多い。
でも、やる気に頼るマネジメントは、いつか息切れする。
天気や体調、機嫌ひとつで変動するものに、現場を委ねるわけにはいかない。
大切なのは、“自然と動けるような設計”を仕込んでおくこと。
たとえば、「施術後の患者に10秒でいいから追加カウンセリングの声かけをする」ことを、オペレーションに組み込む。
「次回予約時に、前回との変化を一緒に確認する」ことをルール化する。
小さなアクションでも、それが日常になれば提案の入口になる。
そしてそれが成約につながれば、「あのひと声が意味あったんだ」と、自然と“気づきの回路”が動き出す。
評価制度も、“やったら報われる”構造がなければ意味がない。
むしろ「ここで自分が成長してる」と感じられるような、対話や振り返りの場があるだけで、人は前に進める。
“自分事化”は、根性論ではなく、設計論。
その発想の転換が、経営者にいま一番求められているのかもしれない。
温度差を“愛”で埋めることはできるか

わかってほしい。でも、わかり合えないのが組織
経営者とは、常に“願っている人”だ。
もっと良くしたい。もっと伝えたい。もっと、スタッフが輝ける現場にしたい。
その想いを、ことあるごとに言葉にしてきたつもりだ。でも、返ってくるのは薄い反応。「ふーん」「そうなんですね」――その温度差に、心が折れそうになることもある。
でも、組織とは、そもそも“わかり合えない人たち”の集まりなのかもしれない。
同じ景色を見ているはずなのに、見ているものが違う。
経営者の“伝えたつもり”と、スタッフの“聞いたつもり”のあいだには、想像以上に深い溝がある。
そしてその溝を、完全に埋めることはきっとできない。
でも、“埋めようとする行為”には意味がある。組織とは、完璧な共感を求める場所ではなく、“わかり合えないことを前提に、それでも並んで立つ場所”なのだと思う。
自分の期待が、自分を追い詰める
「これだけ想いを込めて伝えているのに、どうして伝わらないんだろう」
「もう何度も言っているのに、また同じことが起きる」
そんな日々が続くと、経営者は自分自身を疑い始める。「もしかして、私が悪いのか」「この仕事、向いてないのかな」と。
でも、その苦しさは、あなたが“本気で向き合ってきた証拠”だ。
期待があるから、落胆がある。信じたいから、裏切られたような気持ちになる。
もし本当にどうでもいいなら、何も感じないはずだ。
感情が揺れるのは、まだ信じているからだ。
“変わってほしい”と願うのは、“可能性を諦めていない”からだ。
自分を責めるのではなく、その痛みこそが“愛の副作用”だと、少しだけ自分を許してみてもいい。
理屈を超えた、“まなざし”の力
「何を言うか」より、「どう見つめているか」が、場の空気をつくる。
スタッフは、言葉よりも先に、あなたのまなざしを受け取っている。
怒っているのか、失望しているのか、それとも、まだ信じているのか――。
変わらないスタッフに対して、「どうせ無理」と思って接すれば、その空気は伝染する。
でも、「まだいける」と心から思って接すれば、時間はかかっても、何かが変わることがある。
人は、“期待されている”と感じた瞬間に、ふと前を向くことがある。
それは理屈ではない。ただの言葉でもない。“まなざし”が持つ静かな力だ。
誰かを動かすのは、正論でもプレッシャーでもない。
ただ、「信じているよ」という、ブレない態度なのかもしれない。
経営とは、願いを託し続けること

いかがでしたか?
ここまで読んでくださったあなたは、きっと何度も“伝えよう”としてきた方なのだと思います。
何度も壁にぶつかって、それでもスタッフの可能性を信じてこられたのでしょう。
うまくいかなかった日も、それでも諦めきれなかった日も。
「こうすれば、きっと伝わる」――そんな魔法の言葉は、きっとありません。
でも、「伝わらなくても、伝えつづける」ことでしか、変わらない現場があるのも事実です。
怒らないことが優しさではなく、あきらめないことが優しさになる。
伝わらないと感じたときこそ、目の前のスタッフに、もう一度“まなざし”を向けてみてください。